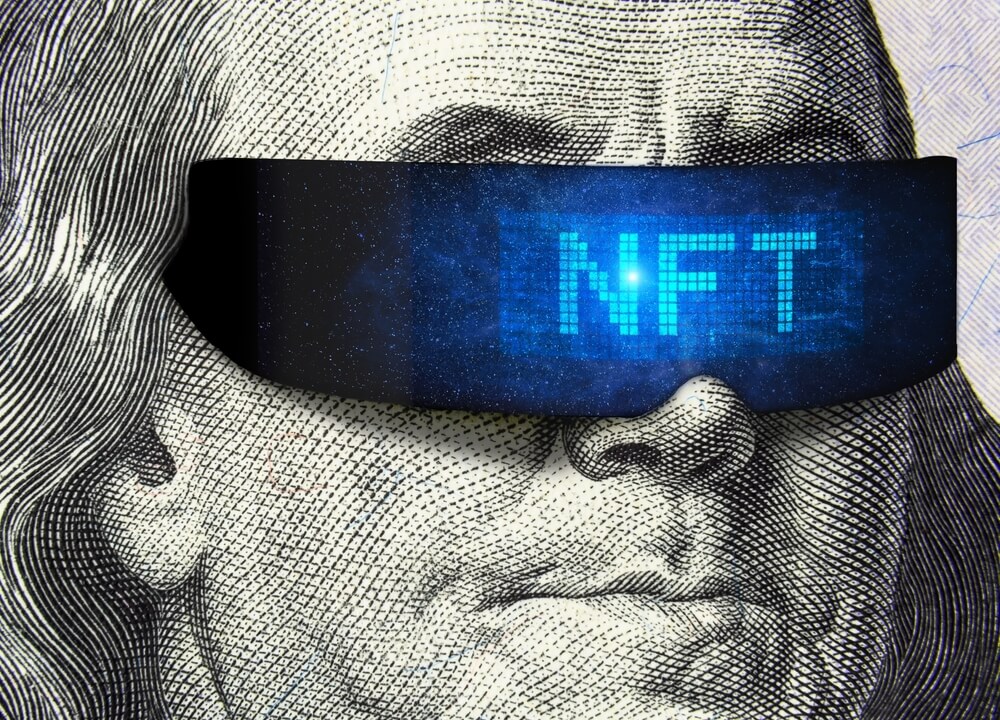仮想通貨(ビットコイン)の税金がやばい理由【FPが解説】


仮想通貨の税金がやばいって本当!?具体的な対策は?

仮想通貨で一攫千金を当て「億り人」となった人たちの中には、その後の税金でかなり苦労された方も多いです。
仮想通貨で得られた利益に対しても当然税金が発生しますので、これから仮想通貨投資を行おうと考えている人は、税金に関する理解が必要不可欠です。
仮想通貨の税金の計算方法や、実際にどのようなケースで税金が発生するのかなど正しく理解しておくことで、前もって節税対策が行えます。
将来的に仮想通貨で大きな利益を得ようと考えている方は、税金面で損しないようにしましょう。
本記事では仮想通貨の税金面に関して、初心者にも分かりやすく解説しています。
最後まで読んでいただくことで、仮想通貨の税金事情に関して正しく理解し、適切な行動が取れるようになるでしょう。
- 仮想通貨の利益は雑所得に分類される
- 仮想通貨を所持しているだけであれば税金はかからない
- 仮想通貨の節税対策を行うことで税金負担を軽減できる
仮想通貨の税金がやばい理由
2017年の仮想通貨ブームにより、日本では約300名の人たちが「億り人」となり、富裕層の仲間りをしました。
しかし、その中には税金に対する配慮が足りず、年度末には多額の納税を迫られてしまい、一転して多額の借金を抱えた人もいました。
そのような背景から、インターネット上で(仮想通貨の税金がやばい…)という噂が立ち、今に至るという訳です。
また、日本政府が仮想通貨を認めたのは、2017年4月1日に施行された「改正資金決済に関する法律」がきっかけだといわれています。
その後、日本では急速に仮想通貨に対する法整備が行われ、税金面に対しても徐々に対策が取られています。
法律的に認められたことで、値上がりしたともいえる2017年の仮想通貨の高騰ですが、その反面、税金で苦労した方も多くいました。
仮想通貨の利益は雑所得に分類される
雑所得とは、利子所得や配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得などに当てはまらない所得を指します。
雑所得は損益通算ができないようになっているため、仮に仮想通貨で赤字が出ていたとしても、所得金額は0となり他の所得と損益を合算できません。
例えば会社員Aさんの給与所得が1,000万円で、仮想通貨で収支がマイナス5,00万円出たとしましょう。
会社員Aさんが実際に得た金額は、500万円(1,000万円ー500万円)にも関わらず、損益通算ができないため、課税額は1,000万円になります。
その上、繰越控除もできませんので、本年度のマイナス分を翌年に持ち越せません。
仮想通貨の税金上の法整備に関しては、まだまだ追いつけていない部分が多く、非常に流動性が高いといえます。
今後もルール変更がある可能性が高いため、現在は利益確定せずにガチホ(ガチでホールドする)している人が多いです。
今はまだ税制上では仮想通貨は不利だといえますので、現時点で大きな含み益を抱えている方は、下手に利確せずに法整備が整うまでガチホするのも一つの手段です。
仮想通貨の税金の計算方法
仮想通貨で得られた利益は雑所得に分類されるため、他の給与所得などと合算して課税する総合課税に該当します。
FX投資等で得られた利益も雑所得に該当しますが、こちらは他の所得と合算して課税されない分離課税になります。
総合課税と分離課税の違いは、簡単にいえば他の所得と合算して課税されるかされないかです。
また所得とは、収入から経費を差し引いた金額を指します。
所得 = 収入 ー 経費
収入をそのまま所得として計上してしまうと、余計に税金がかかってしまうため、できるだけ経費で所得を抑える必要があります。
経費項目としては取得原価や取引手数料、書籍代、セミナー代、通信費、パソコン関連費用、税理士への報酬、確定申告費用などが挙げられるでしょう。
会社員の場合であれば、給料とは別に年間所得が20万円を超えている場合は、確定申告が必要になります。
例えば年間で得られた仮想通貨での所得が、600万円だったとすると以下のような計算式です。
600万円(課税される所得金額) × 20%(税率) - 427,500円(控除額) =772,500円(所得税)
※ 別途「復興特別所得税(2.1%)」が課税されます。

仮想通貨の税金の計算が面倒な人は、仮想通貨専用の自動計算ソフトを活用するのがおすすめです。
仮想通貨で税金が発生する主な3つのケース
- 利益確定したとき
- 他の仮想通貨と交換したとき
- 仮想通貨で商品を購入したとき
仮想通貨投資を行なっている方が必ず抑えておきたいのが、どのような場合に税金が発生するかです。
基本的に税金は、利益が出た時点で発生します。
仮想通貨を持っているだけでは税金はかかりませんので、その点だけでも抑えておきましょう。

仮想通貨の税金の計算は複雑なので個人で判断できない場合は、税理士に相談するなどして対策するのもありです。
利益確定したとき
仮想通貨を購入した後に値上がりしたことを理由に売却し、利益を確定した時点で税金が発生します。
仮想通貨投資を行なっている人の多くは、売却益を狙っている人が大半だと思われますが、他の金融商品同様に仮想通貨でも売却益には税金がかかります。
譲渡価格 ー 譲渡原価(購入時の1BTC当たりの価格 × 売却した数量) = 所得金額
※ 取引上の売買手数料については考慮しない(以降の計算式でも同様)
他の仮想通貨と交換したとき
一見すると仮想通貨同士の売買は、全く問題ないように思えます。
しかし、税務上では一旦持っている仮想通貨を売却し、その後別の仮想通貨を購入したとみなされるため、利益が確定したと判断され税金が発生するという訳です。
ETH購入価格(BTCの譲渡価格) ー 譲渡原価(1BTC当たりの価格 × 支払った数量) = 所得金額
仮想通貨で商品を購入したとき
最近は仮想通貨で他の商品やサービス等を、購入できるシーンも多くなりました。
東京には仮想通貨で支払いができるバーやレストランがあったり、日用品等に関しても仮想通貨での支払いを採用しているお店も少なくありません。
商品価額(BTCの譲渡価額) ー 譲渡原価(1BTC 当たりの価額 × 支払った数量) = 所得金額
仮想通貨の税金は確定申告が必要なの?それとも不要?
以下の条件に該当する人は、確定申告が必要です。
- 給与を受け取っている人:給与収入が2,000万円以下かつ、その他所得が20万円以上ある
- 公的年金を受け取っている人:公的年金収入が400万円以下かつ、その他所得が20万円以上ある
- 被扶養者の主婦や学生など:所得が38万円以上ある
会社員や公務員の方は①に該当するため、仮想通貨もしくはそれ以外の所得の1年間(1月1日から12月31日)の合計金額が、20万円以上ある場合は確定申告が必要です。
逆に仮想通貨投資を行なっているけど、年間の所得が20万円以下だという会社員や公務員等の人は、確定申告は必要ありません。
仮想通貨の確定申告のやり方
仮想通貨の確定申告を行う場合、給与や年金等を受け取っている人は確定申告書A、個人事業主など事業を行なっている人は確定申告書Bを活用します。
申告期間は、通常2月16日~3月15日までです。
実際に確定申告を行う際には、スマホやパソコンを活用してインターネットからでも可能です。
e-TaX(国税電子申告・納税システム)を活用して確定申告を行う際には、1月からでも申告ができます。
具体的なやり方に関しては、国税庁の公式サイトをご確認ください。
また、仮想通貨の評価方法を定める書類(所得税の暗号資産の評価方法の届出書)の提出も必要となりますので、詳細を把握した上で作成するようにしましょう。
仮想通貨の節税対策5選
- 法人化する
- 経費の計上を正しく行う
- 年間20万円以下の利益で確定する
- 内部通算する
- ふるさと納税を活用する
仮想通貨の節税対策にはさまざまなやり方がありますが、全てが全員に適している訳ではありません。
ご自身の状況に合わせた節税対策が必要になりますので、対策内容を正しく理解した上で実行するようにしてください。
法人化する
仮想通貨の節税対策の中でも最も効果が高いのが、法人化です。
| 法人化のメリット | 法人化のデメリット |
| ・税率(所得税より法人税の税率が低い) ・決算期を自由に変更できる ・経費が広く認められる ・所得の分散が図れる ・給与所得控除の利用が可能(自身に人件費が出せる) ・役員退職金の支払いが可能 ・最大10年間赤字の繰越が可能 ・損益通算の可否 | ・設立費用や時間、手間がかかる ・社会保険の負担 ・会計事務所への費用 ・維持経費がかかる ・資金の使い方に制約がある ・税務調査の可能性が高い |
法人化することで仮想通貨取引自体を事業として扱えますので、仮に収支がマイナスになったとしても、最長10年間は繰越が可能です。
その上、所得税よりも法人税の最大税率の方が約22%も低いため、大きな税負担の軽減に繋がります。
- 所得税:所得が4,000万円以上の場合は、住民税と合算して最大55%の税率
- 法人税:住民税等の税率と合算しても最大で約33%の税率
法人化する目安としては、課税所得が800万円以上である場合は、検討してみる価値があるといえます。
個人で判断するのが難しい人は、税理士に相談した上で実行するようにしましょう。
経費の計上を正しく行う
仮想通貨で利益を得た場合は、利益から経費を差し引くことで課税所得を減らすことができます。
仮想通貨の経費には、取引所の手数料や仮想通貨関連に関して学習するために購入した書籍や、セミナー代金等が含まれます。
何が経費になるかは、ハッキリと断言するのは正直難しいです。
とはいえ、控除額となる経費をできるだけ計上することで節税に繋がりますので、判断に迷ったら税理士等に相談してみましょう。
年間20万以下の利益で確定する
給与所得を受け取っている会社員や公務員等の場合、仮想通貨での年間の所得が20万円を超えない限り、確定申告の必要はありません。
そのため、所得税は課税されず税金がかからない訳ですが、年間20万円以下を目安にして利益確定を毎年繰り返すことで節税対策が行えます。
仮に仮想通貨で40万円の含み益を得ている場合は、毎年20万円ずつ利益確定すると所得税は全くかかりません。
ただ、あまりにも仮想通貨での含み益が多い人は、毎年20万円ずつだと焼け石に水なので、他の節税対策を検討しましょう。
内部通算する
内部通算とは、雑所得内で利益と損失を相殺することを指します。
損益通算ができないため他の所得とは相殺できませんが、雑所得内での利益と損失は相殺可能です。
例えばビットコインで100万円の利益を既に計上している上で、アルトコインで含み損が50万円出ているとしましょう。
アルトコインを損切りすると50万円の損失が確定してしまいますが、内部通算することで課税所得は残額50万円(100万円ー50万円)で済みます。
ふるさと納税を活用する
ふるさと納税とは、特定の自治体に対して寄附を行うことで、寄付金の一部から所得税及び住民税を控除できる制度です。
原則として自己負担額の2,000円を除いた金額が、控除の対象となります。
既に仮想通貨の利益での納税額が確定している人は、前もってふるさと納税を活用するのも一つの方法です。
※ 参考サイト:ふるさと納税ポータルサイト|総務省
仮想通貨の税金は納税しなくてもバレない!?【4つのペナルティ】
本人が確定申告を行っていないくても、取引所自体に税務調査が入って全ての取引情報が調査されれば無申告者は特定されます。
仮に仮想通貨で億単位の利益が出ているのにも関わらず無申告だった場合は、最長で7年間遡って税務署は調査が可能です。
故意に無申告だったりすると以下のようなペナルティが課せられますので、くれぐれもやらないようにしましょう。
※ 参考サイト:無申告者に対する調査状況|国税庁
延滞税
延滞税とは、簡単にいったら定められた期日までに、納税しなかった場合に追加でかかる税金です。
原則として期限翌日から翌年2月までは、通常の納税額の7.3%が追加徴収されます。
例えばレンタルDVDの返却期間を過ぎた場合は延滞料金が発生しますが、納税に関しても期日を過ぎると追加料金が発生するという訳です。
※ 参考サイト:延滞税について|国税庁
過少申告加算税
過少申告加算税とは、本来申告すべき金額よりも少なめに記載して、確定申告書を税務署に提出した際に課せられるペナルティです。
税務署から指摘された場合は、本来納めるべき納税額の10%ほどの金額が追加でかかります。
※ 参考サイト:確定申告を間違えたとき|国税庁
無申告加算税
無申告加算税とは、法律で定められた期間までに確定申告を行わなかった場合に、課せられるペナルティです。
正当な理由が何もない状態で確定申告を行わずにいると、通常の課税額に加えて更に15%の加算が行われます。
適用判断は税務署が行うため、指摘があった場合は速やかに確定申告書を提出しましょう。
重加算税
重加算税とは、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税に加えて、過度に悪質なケースに課せられる重いペナルティになります。
最大で50%の重加算税が課せられるため、適応された場合は税務署からはかなり厳しい目で見られている、といっても過言ではありません。
※ 参考サイト:加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし|国税庁
仮想通貨の税金に関するよくあるQ&A
仮想通貨の税金に関する悩みや疑問を抱えている人のために、特に多かった質問内容だけをピックアップし、回答をまとめてみました。
Q:仮想通貨は売るたびに課税されますか?
売る度に課税される訳ではなく、利益が出る度に税金が発生するという考えが正しいといえます。
仮想通貨で税金が発生するのは、以下のような場合です。
- 利益確定したとき
- 他の仮想通貨と交換したとき
- 仮想通貨で商品を購入したとき
Q:仮想通貨の税金の計算をするために、税理士に取引所のAPIコードやシークレットキーを教えるのは危険ですか?
例え信頼している税理士であったとしても、決して取引所のAPIコードやシークレットキー等を教えてはいけません。
各取引所で取引履歴をダウンロードできるようになっていますので、PDFファイル等で送付して計算を行ってもらうようにしましょう。
Q:仮想通貨の税金はいつ払うのですか?
原則3月15日までに所得税の支払いが、完了しなければいけません。
※参考サイト:税金の納付|国税庁
Q:海外の取引所を利用している場合、税金はかかりますか?
海外の取引所を利用している場合でも、税金はかかります。
日本在住の場合は、日本の税制に従って課税されます。
仮想通貨の税金事情を正しく理解して対策を練ろう!
仮想通貨の税金に関する法律は、まだしっかりと整備されていない状況ですので、今後も変更になる可能性が十分考えられます。
現状、税制上では仮想通貨に対しては不利な条件が多いため、税金を気にされている方は利益確定せず、ガチホしておくのが無難だといえます。
とはいえ、節税対策の方法も複数ありますので、ご自身の状況に応じてご紹介した手段を実践してみてください。

仮想通貨に関する収支管理が面倒な方は、クリプタクト(CRYPTACT)やジータックス(Gtax)などの自動計算ソフトを活用するのもおすすめです。